みなさん、こんにちは。
sassiです。
今日は、教室の生徒さんからも詳しく理解をしたい。という
リクエストが非常に多い作業工程、『コバ処理』についてのお話。
レザークラフトの経験者であれば、必ずしも頭を抱えた経験があるのではないでしょうか!?
コバ処理とは、革の断面の処理の事です。
革の特性は勿論の事、革の厚さ・重ねた革の枚数などによっても必要なテクニックは異なります。
私が感じる一番勘違いをされやすい事は・・・
道具や処理剤によって、仕上がりの綺麗さが異なると思われている事です。
逆に言うと、道具や処理剤を変えれば、綺麗な仕上がりになると思われている事。
これは違うと思います。
まずは道具について言うと、道具によって作業性やスピード感が変わったとしても、
仕上がりが変わる訳ではありません。
目的とポイントをしっかりと捉え、確実にアプローチができているかが重要。
処理剤については、それぞれの特徴や向き不向きがあるので、
それらをしっかりと把握し、見た目だけではなく機能と持続性を重視した方が良いと思います。
うまくできる人は、どんな道具でどんな処理剤を使用しても美しく仕上げるし、
そうでない人はその逆です。
大まかな作業は、処理剤を塗る→磨く→ヤスリがけ。
これを1セットとした時に、いったい何セットやれば綺麗になるの!?
と問われる事が数え切れないほどあります。
この捉え方がちょっと違います。
多くの方が、ハッキリと“今、何をどうしたいか”という目的をハッキリさせないままに、
“こなす”という感覚で磨いている人が多い。
その時点で、何らかの対策をしなければいけない状態でも、先へ進んでしまう。
この場合、何十セット磨きをしても、ただコバ面が分厚くなっていくだけで、
根本的な解決には至りません。
逆に、処理剤のひび割れなどを起こします。
何セットやるかは、コバ処理を始める前の状態次第で、この状態こそが最も大事。
状態も革の種類も重ねた枚数も異なるコバ面に対し、
セット数を基準に考えるのは難しいです。

このコバ面には、それぞれ5枚の革が重なっています。
硬さも厚さも種類も異なる革を含め。
分かりやすい、厚めのコバ面を例にしております。
コバ処理の目的は、
・断面の装飾
・革の層の一体化(ボンド層を含む)
・水分など、外的な要因による接着剤の剥がれや劣化防止
など。
革の層に凹凸や段差があるのは見た目的に美しくありません。
触った手触りも、ザラザラしているようでは気になります。
1回1回の、処理剤を塗る作業も、磨く作業も、滑らかにする作業も、
全体として捉えずに、今、何をしたいかという目的を把握し、それを解決する術が大事です。
コバ処理で悩む生徒さんに、言葉で説明しながら、
実際の作業を生徒さんのコバ面で解決してあげると、皆さん納得してくれます。
その上で、道具などにこだわってみるのは良い事と思います。

コバ処理については、もっとしっかりと説明をしなければ伝わらない事と思いますが、
あまりにも記事が長くなってしまうので、これくらいで。
道具についても後日、記事にしたいともいます。
※言葉の表現が下手で、きつく聞こえてしまっていたらすみません(*^_^*)
それでは・・・
ittenのHPはこちら
facebookページはこちら
sassiです。
今日は、教室の生徒さんからも詳しく理解をしたい。という
リクエストが非常に多い作業工程、『コバ処理』についてのお話。
レザークラフトの経験者であれば、必ずしも頭を抱えた経験があるのではないでしょうか!?
コバ処理とは、革の断面の処理の事です。
革の特性は勿論の事、革の厚さ・重ねた革の枚数などによっても必要なテクニックは異なります。
私が感じる一番勘違いをされやすい事は・・・
道具や処理剤によって、仕上がりの綺麗さが異なると思われている事です。
逆に言うと、道具や処理剤を変えれば、綺麗な仕上がりになると思われている事。
これは違うと思います。
まずは道具について言うと、道具によって作業性やスピード感が変わったとしても、
仕上がりが変わる訳ではありません。
目的とポイントをしっかりと捉え、確実にアプローチができているかが重要。
処理剤については、それぞれの特徴や向き不向きがあるので、
それらをしっかりと把握し、見た目だけではなく機能と持続性を重視した方が良いと思います。
うまくできる人は、どんな道具でどんな処理剤を使用しても美しく仕上げるし、
そうでない人はその逆です。
大まかな作業は、処理剤を塗る→磨く→ヤスリがけ。
これを1セットとした時に、いったい何セットやれば綺麗になるの!?
と問われる事が数え切れないほどあります。
この捉え方がちょっと違います。
多くの方が、ハッキリと“今、何をどうしたいか”という目的をハッキリさせないままに、
“こなす”という感覚で磨いている人が多い。
その時点で、何らかの対策をしなければいけない状態でも、先へ進んでしまう。
この場合、何十セット磨きをしても、ただコバ面が分厚くなっていくだけで、
根本的な解決には至りません。
逆に、処理剤のひび割れなどを起こします。
何セットやるかは、コバ処理を始める前の状態次第で、この状態こそが最も大事。
状態も革の種類も重ねた枚数も異なるコバ面に対し、
セット数を基準に考えるのは難しいです。
このコバ面には、それぞれ5枚の革が重なっています。
硬さも厚さも種類も異なる革を含め。
分かりやすい、厚めのコバ面を例にしております。
コバ処理の目的は、
・断面の装飾
・革の層の一体化(ボンド層を含む)
・水分など、外的な要因による接着剤の剥がれや劣化防止
など。
革の層に凹凸や段差があるのは見た目的に美しくありません。
触った手触りも、ザラザラしているようでは気になります。
1回1回の、処理剤を塗る作業も、磨く作業も、滑らかにする作業も、
全体として捉えずに、今、何をしたいかという目的を把握し、それを解決する術が大事です。
コバ処理で悩む生徒さんに、言葉で説明しながら、
実際の作業を生徒さんのコバ面で解決してあげると、皆さん納得してくれます。
その上で、道具などにこだわってみるのは良い事と思います。
コバ処理については、もっとしっかりと説明をしなければ伝わらない事と思いますが、
あまりにも記事が長くなってしまうので、これくらいで。
道具についても後日、記事にしたいともいます。
※言葉の表現が下手で、きつく聞こえてしまっていたらすみません(*^_^*)
それでは・・・
ittenのHPはこちら
facebookページはこちら

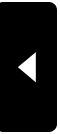

コメント